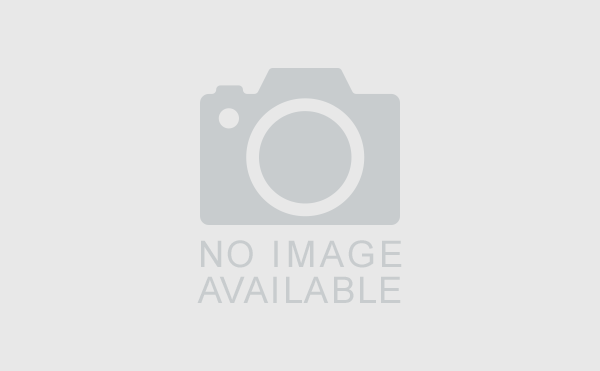WordPressの子テーマの使い方とメリットやデメリット
子テーマの使い方
WordPressの子テーマの使い方は以下の通りです。
1. 子テーマの作成
子テーマは、親テーマの機能を継承しつつ、カスタマイズを加えるためのテーマです。子テーマを作成することで、親テーマのアップデートがあっても、カスタマイズが上書きされることなく保持されます。
子テーマの作り方:
- FTPクライアントまたはファイルマネージャーを使用: WordPressのインストールディレクトリにある
wp-content/themesフォルダ内に新しいフォルダを作成します。フォルダ名は、親テーマ名に-childを付けたものが一般的ですが、任意で構いません(例:twentytwentyfour-child)。 style.cssファイルの作成: 作成した子テーマフォルダ内にstyle.cssという名前のファイルを作成します。このファイルは子テーマの必須ファイルです。style.cssに以下の内容を記述:
/*
Theme Name: My Child Theme (任意の名前)
Theme URI: https://example.com/ (子テーマのURI、任意)
Description: My custom child theme (子テーマの説明、任意)
Author: Your Name (作者名、任意)
Author URI: https://example.com/ (作者のURI、任意)
Template: parent-theme-directory-name (ここには親テーマのフォルダ名を正確に記述)
Version: 1.0.0 (子テーマのバージョン、任意)
Text Domain: my-child-theme (テキストドメイン、任意)
*/重要: Template:の行には、親テーマのフォルダ名を正確に記述してください。この情報がないと、子テーマは機能しません。例えば、親テーマのフォルダ名がtwentytwentyfourであれば、Template: twentytwentyfourとなります。
functions.phpファイルの作成(オプションだが推奨): 子テーマフォルダ内にfunctions.phpという名前のファイルを作成します。このファイルは、親テーマのスタイルシートを適切に読み込むために使用します。
functions.phpに以下の内容を記述:
<?php
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_child_theme_enqueue_styles' );
function my_child_theme_enqueue_styles() {
wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri() . '/style.css' );
wp_enqueue_style( 'child-style',
get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css',
array('parent-style'),
wp_get_theme()->get('Version')
);
}
?>- このコードは、まず親テーマの
style.cssを読み込み、次に子テーマのstyle.cssを読み込みます。これにより、子テーマのスタイルが親テーマのスタイルを上書きできるようになります。
2. 子テーマの有効化
子テーマを作成したら、WordPressの管理画面から有効化します。
- WordPressの管理画面にログインします。
- 「外観」→「テーマ」に移動します。
- 作成した子テーマが表示されているので、「有効化」をクリックします。
3. 子テーマでのカスタマイズ
子テーマを有効化したら、親テーマのファイルを直接編集することなく、安全にカスタマイズを行うことができます。
主なカスタマイズ方法:
- CSSの追加・上書き: 子テーマの
style.cssファイルにCSSを追加することで、親テーマのスタイルを上書きしたり、新しいスタイルを追加したりできます。 例:
/* 子テーマのstyle.cssに追加 */
body {
font-family: "メイリオ", Meiryo, sans-serif;
color: #333;
}
.site-title a {
color: #0073aa;
}テンプレートファイルの変更: 親テーマのテンプレートファイル(例: header.php, footer.php, page.php, single.phpなど)を子テーマフォルダにコピーし、そのファイルを編集することで、レイアウトや表示内容を変更できます。 注意: 親テーマのファイルをコピーして編集した場合、親テーマがアップデートされても子テーマの変更は維持されますが、親テーマ側のそのファイルが大幅に変更された場合は、子テーマ側のファイルとの間で競合が発生する可能性があります。
例: header.phpをカスタマイズしたい場合
- 親テーマの
header.phpを子テーマフォルダにコピーします。 - コピーした子テーマの
header.phpを編集します。
functions.phpへの機能追加: 子テーマのfunctions.phpにPHPコードを記述することで、新しい機能を追加したり、既存の機能を変更したりできます。親テーマのfunctions.phpの内容はそのまま引き継がれます。 例: カスタム投稿タイプを追加したり、ショートコードを登録したり。
<?php
// (上記で記述したスタイルシート読み込みコードの後に追記)
// カスタム投稿タイプ「お知らせ」を追加
function create_news_post_type() {
register_post_type( 'news',
array(
'labels' => array(
'name' => __( 'お知らせ' ),
'singular_name' => __( 'お知らせ' )
),
'public' => true,
'has_archive' => true,
'menu_position' => 5,
'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail' ),
)
);
}
add_action( 'init', 'create_news_post_type' );
?>子テーマを使うメリット:
- 親テーマのアップデートに対する安全性: 親テーマがアップデートされても、子テーマでのカスタマイズが上書きされることがありません。これにより、安心して親テーマを最新の状態に保つことができます。
- カスタマイズの整理: 親テーマのファイルを直接編集するのではなく、子テーマにカスタマイズをまとめることで、どこをどのように変更したか分かりやすくなります。
- テーマの切り替えが容易: 子テーマを無効化すれば、親テーマの元の状態に戻すことができます。
注意点:
- 親テーマの依存: 子テーマは親テーマに依存しています。親テーマがインストールされていないと、子テーマは機能しません。
- 親テーマの削除: 親テーマを削除すると、子テーマも機能しなくなります。
これらの手順とポイントを押さえることで、WordPressの子テーマを効果的に活用し、安全かつ柔軟なWebサイトのカスタマイズが可能になります。
子テーマのデメリット
WordPressの子テーマにはいくつかのデメリットがあります。主なものを以下に挙げます。
1. 学習コストと複雑性:
- 初期の学習曲線: 子テーマの仕組み、親テーマとの関係性、テンプレート階層などを理解するには、ある程度の学習が必要です。特にWordPress初心者にとっては、少しハードルが高く感じられるかもしれません。
- コードの追跡と管理: 親テーマと子テーマの両方にコードが存在するため、どこでどのコードが適用されているのかを把握するのが複雑になることがあります。特に、複数の開発者が関わるプロジェクトでは、混乱を招く可能性があります。
2. デバッグの難しさ:
- 問題の特定: 親テーマ、子テーマ、プラグインなど、複数の要素が絡み合うため、問題が発生した際に原因を特定するのが難しくなることがあります。
- テーマファイルの重複: 誤って親テーマから子テーマにテンプレートファイルをコピーし、その内容を変更し忘れた場合など、意図しない挙動や表示のバグを引き起こす可能性があります。
3. 更新時の注意点:
- 親テーマの更新との兼ね合い: 親テーマが大幅に更新された場合、子テーマで上書きしている部分が、新しい親テーマの機能と競合したり、意図しない表示になったりする可能性があります。
- 頻繁な確認作業: 親テーマの更新後には、子テーマが正しく機能するかどうかを常に確認する必要があります。特に、カスタマイズの多いサイトでは、この確認作業が負担になることがあります。
4. 開発環境の管理:
- テスト環境の必要性: 親テーマと子テーマの両方を管理するため、本番環境に影響を与える前に、開発環境やステージング環境で十分にテストを行うことが強く推奨されます。これにより、環境設定やデプロイのプロセスが複雑になることがあります。
5. 機能の制限と冗長性:
- 親テーマの機能に依存: 子テーマは親テーマの機能を拡張するものであり、親テーマが提供していない機能を追加するには、プラグインの使用や子テーマでの大幅なコード記述が必要になります。
- カスタマイズの限界: 親テーマの構造が非常に特殊であったり、カスタマイズが難しいように設計されている場合、子テーマでの自由なカスタマイズが制限されることがあります。その結果、似たようなコードが親テーマと子テーマの両方に存在することになり、冗長性が生じる可能性があります。
6. パフォーマンスへの影響(稀):
- ファイルの読み込み: ごく稀に、子テーマと親テーマの両方のスタイルシートやスクリプトが適切に最適化されていない場合、わずかにページの読み込み速度に影響を与える可能性がないとは言えません。しかし、これは一般的には無視できるレベルであり、正しく実装されていれば大きな問題にはなりません。
これらのデメリットはありますが、子テーマはWordPressサイトを安全かつ持続的にカスタマイズするための非常に強力なツールであることに変わりはありません。デメリットを理解し、適切に対処することで、効果的に子テーマを活用することができます。
個人事業主・中小企業向けWordPress 有料テーマ Emanon
![]() は、Web集客やビジネスの成果を重視する企業サイトにとって、非常に強力なツールとなり得ます。シンプルで信頼感のあるデザインと、充実した集客機能がその大きな魅力です。ただし、デザインの好みやWordPressの習熟度によっては、使い始めに少し学習が必要になるかもしれません。
は、Web集客やビジネスの成果を重視する企業サイトにとって、非常に強力なツールとなり得ます。シンプルで信頼感のあるデザインと、充実した集客機能がその大きな魅力です。ただし、デザインの好みやWordPressの習熟度によっては、使い始めに少し学習が必要になるかもしれません。
WordPressテーマのEmanon(エマノン)は、子テーマが配布されています。
特に有料版の「Emanon Pro」「Emanon Business」などを購入すると、親テーマのファイルに加えて、子テーマのzipファイルも一緒にダウンロードできるようになっています。
子テーマを使うメリット
子テーマを使う最大のメリットは、テーマのカスタマイズが安全に行えることです。
WordPressのテーマは、新しい機能の追加や不具合の修正のために定期的にアップデートされます。子テーマを使っていない場合、テーマファイルを直接編集していると、アップデートの際に編集内容がすべて上書きされて消えてしまいます。
しかし、子テーマを使えば、親テーマはアップデートしても子テーマのカスタマイズ内容はそのまま残るため、安心してテーマを最新の状態に保つことができます。
もし、これからEmanonでブログやサイトを構築されるのであれば、必ず子テーマをインストールして使用することをおすすめします。