WordPressブロックエディタのグリッドとカラムの使い方
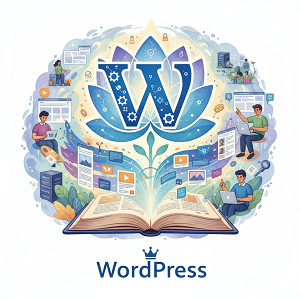
目次
1. WordPressの標準ブロックエディター(Gutenberg)の「グリッドブロック」または関連ブロックを使う
WordPressでグリッドレイアウトを作成する方法はいくつかありますが、主に以下の2つの方法があります。
- WordPressの標準ブロックエディター(Gutenberg)の「グリッドブロック」または関連ブロックを使う
- グリッドレイアウト用のプラグインを使う
それぞれの方法について詳しく説明します。
WordPress 5.0以降で採用されているブロックエディター(Gutenberg)には、レイアウトを組むための便利なブロックがいくつかあります。
- グリッドブロック:
- WordPress.comのサポートページや、一部のテーマで提供されている「グリッドブロック」は、コンテンツを整理し、カラム数や配置を調整できるコンテナブロックです。
- 使い方:
- 新しいブロックを追加する際に、
/gridと入力してEnterを押すか、ブロック挿入ツールから「グリッド」を検索して追加します。 - グリッドブロックを追加すると、通常はカラム数を選択する画面が表示されます。ここで必要なカラム数(例:2カラム、3カラム)を選びます。
- 各カラムの中に、さらに別のブロック(画像、段落、見出しなど)を追加していきます。
- グリッドブロックの右側の設定サイドバーで、カラム幅の自動サイズ指定や手動サイズ指定、カラム間の余白などを調整できます。
- また、グリッド内の個々のブロックの配置(垂直方向など)も設定できます。
- 新しいブロックを追加する際に、
- 特徴: 自動でレスポンシブ対応してくれるため、モバイル表示でもレイアウトが崩れにくいのがメリットです。
- カラムブロック:
- こちらもブロックエディターの標準機能で、複数のカラムにコンテンツを配置するのに使います。
- 使い方: 「カラム」ブロックを追加し、希望するカラム数(2カラム、3カラムなど)を選択します。各カラムの中に、他のブロックを追加していきます。
- グリッドブロックとの違い: グリッドブロックの方がより柔軟なレイアウト設定ができる傾向がありますが、カラムブロックでも簡単なグリッドは作成可能です。
- グループブロックのグリッドバリエーション(テーマによる):
- 一部のテーマやGutenbergプラグインの機能として、通常のグループブロックにグリッドレイアウトのオプションが追加されている場合があります。これにより、既存のブロックをまとめてグリッド化することも可能です。
ブロックエディターでのグリッドのポイント:
- 直感的な操作: ブロックエディター上で視覚的にグリッドを構築できるため、初心者でも比較的簡単に利用できます。
- レスポンシブ対応: 基本的に自動でデバイスサイズに合わせてレイアウトが調整されます。
- リスト表示の活用: 編集画面上部の「リスト表示」を使うと、ブロックの階層構造が分かりやすくなり、グリッドブロック内のブロック選択や移動がスムーズに行えます。
2. グリッドレイアウト用のプラグインを使う
より複雑なグリッドレイアウトや、特定の用途に特化したグリッド表示(投稿一覧、ポートフォリオ、ギャラリーなど)を実現したい場合は、プラグインの利用が非常に有効です。
代表的なグリッドプラグインとその特徴をいくつか挙げます。
- Essential Grid:
- 多機能なグリッドビルダープラグインで、画像、ポートフォリオ、ブログ記事、製品など、さまざまなコンテンツをグリッド形式で表示できます。
- 投稿、ページ、カスタム投稿タイプ、WooCommerce、ギャラリーなど、多様なコンテンツソースに対応しています。
- ナビゲーション、フィルタリング、ソートオプション、様々なスキンの選択肢があり、高度なカスタマイズが可能です。
- Media Grid:
- ビジュアルグリッドビルダーを提供し、ドラッグ&ドロップでアイテムの追加、並べ替え、サイズ設定が可能です。
- ダイナミックグリッドの作成もサポートしており、グリッドレイアウトを設定後、希望のコンテンツタイプを選択すると、自動的にグリッドが埋められます。
- Layout Grid Block (WordPress.orgで入手可能なプラグイン):
- Gutenbergブロックとシームレスに連携し、レスポンシブなカラムレイアウトを簡単に作成できます。
- 溝(カラム間の間隔)のサイズ変更や、エンドガターの追加・削除なども可能です。
- Post Grid (プラグイン):
- WordPressの投稿やページをグリッド形式で表示することに特化したプラグインです。
- 表示する投稿のカテゴリ、タグ、投稿タイプ、日付などでフィルタリングしたり、レイアウトの種類、カラム数、表示する情報(タイトル、抜粋、画像など)を細かく設定できます。
プラグインを使う際のポイント:
- 機能の豊富さ: ブロックエディターの標準機能では難しい、高度なフィルタリング機能やソート機能、豊富なデザインテンプレートなどが利用できます。
- 用途に応じた選択: ポートフォリオサイト向け、ブログ記事一覧向けなど、プラグインによって得意な分野が異なります。目的に合わせて選びましょう。
- 学習コスト: プラグインによっては設定項目が多く、使いこなすまでに時間がかかる場合があります。
グリッドレイアウト作成の一般的な手順(まとめ)
- 目的を明確にする: どのようなコンテンツを、どのようなレイアウトで表示したいのかを決めます。
- 方法を選択する:
- シンプルなグリッドで十分なら、ブロックエディターの「グリッドブロック」や「カラムブロック」を試してみる。
- より高度な機能や、特定のコンテンツ(投稿一覧など)をグリッド表示したい場合は、対応するプラグインを探す。
- 実際に作成する:
- ブロックエディターの場合:
- 新規ページまたは投稿を作成し、ブロックエディターを開きます。
- 「+」アイコンをクリックして「グリッド」または「カラム」ブロックを追加します。
- 表示されるオプションに従ってカラム数などを設定し、各カラムにコンテンツを追加します。
- 右サイドバーのブロック設定で、詳細なレイアウト調整を行います。
- プラグインの場合:
- WordPressの管理画面から「プラグイン」>「新規追加」で目的のプラグインを検索し、インストール・有効化します。
- プラグインの指示に従って、グリッドの作成や設定を行います。(多くのプラグインは、独自の管理画面やショートコード、またはブロックとして機能を提供します。)
- 作成したグリッドを、ページや投稿に挿入します。
- ブロックエディターの場合:
ご自身のWordPress環境(テーマや目的)に合わせて、最適な方法を選んでみてください。
カラムの使い方
WordPressのカラムは、記事や固定ページ内でテキストや画像を横並びに配置するために使用する非常に便利な機能です。主に「カラムブロック」と呼ばれる機能を使って実現します。
ここでは、WordPressのカラムの使い方について詳しく解説します。
1. カラムブロックの追加方法
- 投稿または固定ページの編集画面を開く: WordPressの管理画面から、新しい投稿を作成するか、既存の投稿や固定ページを編集する画面に移動します。
- ブロックを追加:
- コンテンツを追加したい場所で「+」ボタンをクリックします。
- ブロック検索欄に「カラム」と入力するか、「レイアウト要素」の中から「カラム」を選択します。
/(スラッシュ)を入力し、「カラム」と入力しても追加できます。
- カラムのレイアウトを選択: カラムブロックを追加すると、事前に定義された様々なカラムレイアウト(例:50/50、33/66、均等3カラムなど)が表示されます。あなたの希望するカラム数や幅の比率を選択します。最大6カラムまで設定できます。
2. カラムへのコンテンツ追加
カラムブロックを挿入すると、選択したカラム数に応じて複数のカラムが生成されます。それぞれのカラムの中に、任意のブロック(段落、画像、見出し、リストなど)を追加することができます。
- 各カラム内の「+」をクリック: カラムの中に表示されている「+」アイコンをクリックします。
- ブロックを選択して追加: 追加したいブロックを選択し、コンテンツを入力または挿入します。
3. カラムのカスタマイズ
カラムブロックには、柔軟なカスタマイズオプションがあります。
3.1. カラム数と幅の変更
- カラム全体を選択: カラム数や全体の幅を変更したい場合は、外側の「カラムブロック全体」を選択します。
- サイドバーで設定: 画面右側のサイドバーにある「ブロック」タブ(歯車アイコン)を選択します。
- カラム数: 「カラム」のスライダーを動かすか、数字を直接入力してカラム数を変更します。
- カラム幅: 個々のカラムを選択した状態で、右側のサイドバーの「カラム設定」から幅のスライダーを動かすか、任意の数字(%やpx)を入力して幅を調整します。通常は
%で設定するのがおすすめです。
3.2. 配置の調整
- 垂直方向の配置: カラム全体を選択した状態で、各カラム内のコンテンツの垂直方向(上揃え、中央揃え、下揃えなど)の配置を調整できます。
- 水平方向の配置: 一部のテーマや拡張機能では、コンテンツの水平方向の配置も調整できます。
3.3. その他の設定(テーマやプラグインによる)
使用しているWordPressテーマや追加しているプラグインによっては、以下のような拡張機能が提供されることがあります。
- 背景色や枠線の設定: カラムの背景色を設定したり、各カラムに枠線を追加したりできます。
- 余白(パディング・マージン)の調整: カラムの内側や外側の余白を細かく設定できます。
- レスポンシブ設定: スマートフォン表示時のカラムの挙動(例:PCでは2カラムだが、スマホでは1カラムに自動的に切り替わる)を設定できます。多くの場合はデフォルトでレスポンシブに対応していますが、詳細な制御ができる場合があります。
4. カラム使用時のポイントと注意点
- 外側カラムと内側カラム: カラムブロックは、全体のレイアウトを制御する「外側カラム(親ブロック)」と、その中に入る個々のコンテンツを格納する「内側カラム(子ブロック)」で構成されています。設定を行う際は、どちらのブロックを選択しているかを意識することが重要です。
- ブロックナビゲーションの活用: 複雑なレイアウトになる場合、画面左下の「ブロックナビゲーション」を活用すると、現在選択しているブロックの位置関係を把握しやすくなります。
- レスポンシブデザイン: ほとんどのWordPressテーマとカラムブロックは、モバイルフレンドリーなデザインに対応しています。通常、画面幅が狭くなると自動的にカラムが縦並びになるように調整されます。
- プラグインによる機能拡張: 標準のカラムブロックの機能だけでは物足りない場合、ElementorやGutenberg Blocksなどのページビルダープラグインや、カラム機能に特化したプラグイン(EditorsKitなど)を使用することで、より高度なレイアウトやデザインが可能になります。
WordPressのカラムブロックを使いこなすことで、情報を整理し、視覚的に魅力的なコンテンツを作成することができます。色々なレイアウトを試して、あなたのサイトに合った表現を見つけてみてください。



